- 参謀の特長
- ベルロジック株式会社 代表取締役 経営学修士(MBA)メンバーの中でも、異色の経歴を持つ。 前職は、事業者向け専門の「ナニワの金融屋」であり、30代後半までの15年間の経験の中で、約500社を超える倒産と間近に関わってきた。 自称 マネジメント数学研究家(暇さえあれば、ビジネスと数学の交わり方をユーモアたっぷりに伝える工夫をしている)。
コラム
参謀 青木 永一
遊ぶように学ぶ ~知識を楽しみ、定着させる力~
まじめに学んでいるビジネスパーソンほど、「学んだはずなのに、使えない…」「記憶に残っていない…」といった悩みを抱えているのではないでしょうか。
書籍、セミナー、会話……、私たちは日々、何かしらの知識や気づきを得ています。しかし、それが血肉となって活用されているかと問われれば、自信を持ってうなずける人は少ないかもしれません。
本コラムでは、知識がなぜ定着しにくいのかを掘り下げ、その対策として「記憶」「言語化」「楽しむ」という3つの視点から、“学びを生かす習慣”について考えていきます。
目次
驚きより、“引き出しの再発見”こそが成熟の証
学びを重ねた人ほど、「まったく知らなかった」と驚く機会は減っていきます。その代わりに、「たしかに以前、どこかで読んだ(聞いた)気がする」と、記憶の底から知識が再浮上してくることが増えてきます。
私たちの“知識の倉庫”には、多くの情報が眠っています。問題は、それを必要なときに適切に引き出せるかどうか。そこに“学びの定着”の鍵があります。
書いて(読んで)終わりでは、学びは残らない
ノートにまとめて満足してしまう。「見返せばいいや」と思って結局開かない。そして、必要なときに「あれ、どこに書いたっけ?」となる。
これは、“学んだつもりで終わってしまう症候群”とも言える、よくある現象です。
現実には、日々の業務で次から次へと課題が押し寄せ、過去の学びをゆっくり振り返る余裕などありません。だからこそ、“その瞬間にどう使うか” “いつ引き出しを開けるか”が定着を大きく左右します。
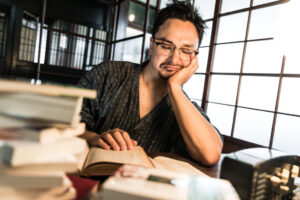
学びを「記憶」させる3つの条件
学びを定着させるために、私が有効だと考えるのは次の3つです。
・メモ魔になること
学びは記録しなければ、雲散霧消するのが人の常です。スマホやノートで「いつでも見返せる」仕組みを持つことが定着のための前提条件となります。人の記憶はアテにはなりません。そのため、とにかくメモを取ることを心掛けるようにすることです。
・隙間時間にランダム再生すること
通勤中や移動中など、ちょっとした時間にメモを見返すことで定着する確率は随分と高まります。記憶は思い出すことで定着すると言われます。とにかく隙間時間にランダムに見返すことを習慣づくりが定着においては重要になります。
・言語化し、静かに自分と対話すること
「自分の言葉」でメモに取った知識を再構成することで、ブラッシュアップを図ります。その過程で思考がクリアになり、さらなる深掘りへとつながります。まさに”記憶に刻む”という状態への能動的な行為に他なりません。
まとめると、隙間時間に気の向くままメモをランダムに見返しながら、表現を整えたり語彙を更新したりすることで、学びを定着させるのです。こうした一連のプロセスを意識的に繰り返すことが、自分の中の知識を成熟させ、定着へとつながるのではないでしょうか。
「楽しさ」が定着を加速させる
知識は、楽しむためのものでもあります。一見するだけでは関連のない情報同士をつなげてみたり、ジャンルを越えて組み合わせたりすることで、新しい発見や面白さが生まれます。
たとえば、
・化学 × 詩
化学反応の“結びつき”と、詩の比喩の“言葉の結びつき”は、実は構造的に似ているかもしれません。
どちらも“条件が揃えば反応する”という前提がある。そう捉えると、詩を読む視点や言葉を紡ぐ感性に、ちょっとした変化が生まれるかもしれません。
・囲碁 × ビジネス会議
囲碁では“先手が主導権を握る”とよく言われます。これは、会議における「議題設定力」に似ているのかもしれません。
先に場を整えた者が、議論の流れを自然に導いていく。そう考えると、囲碁の戦術は会議運営にも応用できると言えるのではないでしょうか。
・ミステリー小説 × 経済ニュース
複雑な経済ニュースも、「伏線(予兆)」→「どんでん返し(政策変更)」→「真犯人(真因)」というミステリー小説の構造で読めば、ストーリーとして理解しやすくなり、またニュースを深堀りする動機にもなるのではないでしょうか。
次にご紹介する「数学的思考 × 経営課題」のたとえは、前述の内容と比べるとより実務寄り(現実的)ではありますが、私自身が「数学」の考え方で思考を巡らせるのが好きなこともあり、補足的に述べさせていただきます。
※数学的思考×経営課題
数学の関数グラフでは、時間と変数の関係性を可視化できます。この発想は、経営の中期計画やKPI設定にも応用できるのかもしれません。
たとえば、新商品投入から半年間の売上変動をグラフ化したとき、どの施策がどの時点で影響を与えたかが曲線に現れます。そうすると、「あの施策は失敗だった」という直感的評価ではなく、「初動は悪かったが、第3週目以降に効き始めている」といった時間軸での評価が可能になると考えられないでしょうか。
数学的な視点とは、感覚ではなく関係性を捉える力とも言えます。
経営においても、数値を“波”として読み取る力が求められる、そのように捉えることができるかもしれません。
意味を求めすぎず、知識を遊ぶように扱うことで、脳は活性化し、定着力も高まるものだと考えています。
学びは「知る」より「好む」そして「楽しむ」へ
孔子はこう語りました。
『子曰、知之者不如好之者、好之者不如楽之者』(知る者は好む者に如かず。好む者は楽しむ者に如かず)
つまり、知っているだけでは不十分で、好きになること、そして楽しむことが最も強いということです。
遊ぶように学び、実験のように試し結果を受けてまた活かす、これこそが学びによる自分自身の進化、自己肯定につながる形ではないでしょうか。
そして、こうした環境が備わっている職場こそが、「心理的安全性」を育む土壌にもなるのだと確信しています。
おわりに
学びとは、ただ知識を取り込むことではなく、日常の中で活かす“自分の武器”として定着させること他なりません。
記録する。見返す。言語化する。つなげて遊ぶ。そうやって“遊ぶように学ぶ”ことが、大人のたしなみだと私は思います。
もちろん、身体を動かし、経験と結びつけることに勝る定着はありません。しかし、すべての学びが行動を伴わなければならないわけではない。その余白を持つこともまた、成熟した学びの姿ではないでしょうか。
参謀学Lab.研究員 青木 永一

