- 参謀の特長
- ベルロジック株式会社 代表取締役 経営学修士(MBA)メンバーの中でも、異色の経歴を持つ。 前職は、事業者向け専門の「ナニワの金融屋」であり、30代後半までの15年間の経験の中で、約500社を超える倒産と間近に関わってきた。 自称 マネジメント数学研究家(暇さえあれば、ビジネスと数学の交わり方をユーモアたっぷりに伝える工夫をしている)。
コラム
参謀 青木 永一
再編のうねりに挑む ~自動車整備業界から読み解く中小企業の生存戦略~
目次
はじめに
中小企業を取り巻く環境は、依然として厳しさを増しています。帝国データバンクの景気動向調査や倒産・休廃業レポート、そして2025年版の中小企業白書を読んでいた際、「自動車整備業界」に関するデータにたまたま目が留まりました。
円安、物価高、人手不足という三重苦のなか、休廃業件数が過去最多を記録し、倒産件数を加えれば約450件に達しているとのことです。
この数字を目にしたとき、他人事ではないという感覚を覚えました。というのも、私自身が現場で向き合ってきた中小企業の姿と、不思議なほど重なっていたからです。本コラムでは、資料から目にした整備業界の状況を入り口に、中小企業が置かれているリアルを綴ってみたいと思います。
数字の奥にある構造的な問題
整備業界に限らず、どの業界においても部品調達費やエネルギーコスト、人件費など、あらゆる費用が高止まりしています。そこに少子高齢化による顧客基盤の縮小が追い打ちをかけ、さらに深刻なのが人手不足という問題です。
自動車整備業界では、特に整備士の高齢化と若手入職者の減少により、「仕事はあるのに受けきれない」、そんな機会損失が各地で発生しています。業界特有の資格制度や現場慣行も影を落としており、これは単なる景気の波ではなく、構造的な問題にほかなりません。
最近では、「需要減や価格上昇のような“目に見える変化”よりも、実は “人が集まらない”という “ 目に見えにくい問題” のほうが深刻だ」と語る声を、耳にすることが増えてきました。
「守るか、攻めるか」選択の岐路に立つ
人手不足は、もはやどの業界にも共通する課題です。賃上げによって人材確保を試みる企業も多く見られます。しかし、すでに労働分配率が8割近い企業にとって、その原資を捻出するのは容易ではありません。
ここで求められるのは、状況に流される「守り」ではなく、価格設定と生産性向上を視野に入れた「攻め」の姿勢です。
中小企業白書では、マークアップ率(価格の上乗せ率)が注目されています。マークアップ率が高い企業ほど、経常利益率や設備投資、賃金水準も高い傾向にあるという分析は、適切な価格設定こそが企業体質を強化する鍵であることを示唆しています。
価格を語る前に、数字を語れるか
価格転嫁の難しさは、私自身も複数の企業で管理職を務めるなかで、何度も実感してきました。価格交渉において大切なのは、まず自社のコスト構造を正確に把握することです。それがあってこそ、原価に基づいた説得力のある価格提示が可能になります。
「高い」と言われることを恐れるのではなく、「なぜこの価格なのか」を説明できる状態を作る。それはすべての業種に共通する課題だと思います。決算資料を備えているにかもかかわらず、実情は経営陣がどんぶり勘定で、自社のコスト構造について把握できていないようでは、価格交渉で成果が出ないのも無理はありません。
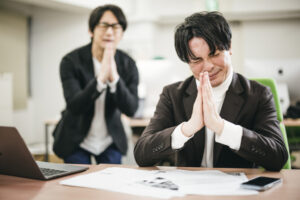
変化は「できること」から動き出す
中小企業白書では、さまざまな成功事例が紹介されています。たとえば、身の丈に合ったDXの推進、未経験人材の育成、下請けからの脱却、地域資源を活かした輸出挑戦など。どれも、「自分たちにできる範囲で」打たれた戦略的な一手でした。
私が関わってきた企業のなかにも、似た取り組みを行って成果を上げた例があります。たとえば、熟練技術者の手作業を動画で記録し、それを新入社員教育の教材として活用したことで、技術継承の道を切り拓いた製造業。あるいは、日報の電子化によって部品消費の履歴を可視化し、業務のボトルネックを特定。作業動線を再設計したことで生産効率が上がり、営業利益が15%改善した企業もありました。
いずれも、「まずはできることから始める」という姿勢が功を奏した事例です。
成熟した組織は「変化の技術」を持っている
変化への投資は、一見すると目先の利益を削る行為のように見えるかもしれません。しかしそれは、「生き残るための備え」と捉えるべきです。
整備業界もまた、EV(電気自動車)やADAS(先進運転支援システム)といった技術革新の波を避けることはできません。この変化にどう向き合うかは、まさに今からの布石にかかっています。
成長を遂げている企業に共通するのは、「変化に向き合う技術」を持っていること。これは精神論でも感性でもなく、変化を歓迎し、挑戦する姿勢が文化として根づいているかどうか、その違いです。
おわりに
生成AIをはじめとする技術革新に象徴されるように、時代の変化は加速度的に進んでいます。もはや、変化を待ち構えるのではなく、自社で変化を起こせるかどうかが問われる時代です。
「今はその時期じゃない」「状況が落ち着いたらにしよう」、そんな “やらない理由” が先に浮かんだとき、変化への意志は自然と鈍ります。
けれど、変化に本当に必要なのは、“正しさ”ではなく“覚悟”なのかもしれません。
「小さな一歩でいい、まずは動く」。その意思が、突破口をひらく力になります。
いま、経営において最も求められているのは、「変化に向かう覚悟」と「変化を起こす技術」、そして「その変化をともにする人材を信じる勇気」ではないでしょうか。
参謀学Lab.研究員 青木 永一

