- 参謀の特長
- ベルロジック株式会社 代表取締役 経営学修士(MBA)メンバーの中でも、異色の経歴を持つ。 前職は、事業者向け専門の「ナニワの金融屋」であり、30代後半までの15年間の経験の中で、約500社を超える倒産と間近に関わってきた。 自称 マネジメント数学研究家(暇さえあれば、ビジネスと数学の交わり方をユーモアたっぷりに伝える工夫をしている)。
コラム
参謀 青木 永一
得意の外側にある、“貢献寿命” の伸びしろ
目次
得意を伸ばすだけが道ではない
「苦手の克服よりも、得意をさらに伸ばせばいい」
これは自己啓発やビジネスの現場でもよく耳にするアドバイスです。確かに、得意を活かすほうが効率的で成果にもつながりやすいのは間違いありません。そうできる環境があるなら、それに越したことはないでしょうし、私自身もそのような方針を語る方々を尊敬しています。
ただ、私が日々向き合っている中小企業の現場、とりわけ人手不足や業務の属人化といった課題が山積する環境では、「得意を伸ばすだけ」では立ち行かない現実があります。むしろ、各人が“苦手”と向き合い、それを少しでもほぐしていく過程にこそ、組織や個人の可能性を広げる鍵があると、現場で実感してきました。
本稿では、そうした「苦手」への向き合い方について、特に中高年におけるリスキリングの意義を軸に、再解釈・再定義の可能性を掘り下げていきます。
「苦手」は記憶がつくる思い込みにすぎない
苦手意識とは、あるタイミング、ある条件のもとで形成される一時的なラベルに対する認識のことかもしれません。たとえば、食べ物であればその時の体調や調理法が、また一般的には忌み嫌われがちな数学であれば先生との相性や、つまずいたポイントでの当時の理解力が左右している可能性もあるでしょう。つまり、“苦手”とは、今振り返ってみれば、当時のごく短い一場面での体験に過ぎず、そのときの文脈がつくり出した一種の“錯覚”だったのかもしれません。
苦手と再び向き合う機会を持つことの効能
私がそう考えるようになったのは、自身の経験に深く起因しています。学生時代の私は、今とは異なり、数学を「好きだ」とはまったく言えませんでした。先生との相性や、学ぶ内容に意味を見いだせなかったことなど、さまざまな要因が重なり、次第に苦手意識が形成されていったのです。今振り返れば、それらは未熟な感性や浅はかな思考、経験の乏しさから生まれた、一方的かつ自己都合的な解釈に過ぎなかったのだと思います。
しかし30代半ばを迎える頃、仕事を通じて数学的な考え方の必要性を痛感し、基礎から学び直しを始めました。すると、当時は難解だった概念や具体的な問題が、むしろ興味深く感じられるようになり、いまでは「得意」とまでは言えませんが、数学の講座や問題に日々触れることが習慣となり、趣味と呼べるほどになっています。
この経験を通じて私が確信したのは、ごく当たり前のことかもしれませんが、「苦手を克服するには、一定量の取り組みが不可欠だ」ということです。そして、その“量”がある閾値を超えたとき、質的な変化が生まれる転換点が訪れるのです。
中高年における学び直しの意味
若い時期であれば、その“量”をこなすための時間が確保しやすいだけでなく、エネルギーの持続力や習慣化の柔軟性といった点においても有利です。しかし、中高年になると、単に時間的な制約が生じるだけでなく、日々の生活や責任が多層的に絡み合い、可処分時間の「質」自体が変化していることに気づかされます。たとえば、突発的な介護や健康上の配慮、職場での立場や家庭内の役割など、時間を使う際の優先順位や心身の余白の持ち方が、若いころとはまったく異なるものになっているのです。
だからこそ、中高年が「苦手」と改めて向き合うには、これまでに培ってきた経験や知識、思考を土台に、それまで苦手としていた対象に社会や心理、組織などと紐づけた新たな理解の文脈を与えることが重要です。そうすることで、より効率的かつ効果的で、本質に根ざした学びが実現できると確信しています。
学びを自分のものとして引き寄せることができれば、自然と継続が生まれ、やがては周囲からの評価にもつながっていきます。その好循環の中で、ビジネスの現場においても、応用に向けた自発的な意思や挑戦心が芽生え、理想とする姿への歩みが着実なものになっていくのではないでしょうか。

最適化の罠から抜け出す
ここで、少し視点を変えてみましょう。
私たちはしばしば、「情報の最適化」という罠に陥ることがあります。たとえば YouTube では、自分の関心のある動画ばかりを視聴していると、アルゴリズムがそれに反応して、似たような情報を次々と届けてきます。一見便利に思える仕組みですが、その反面、新たなテーマに触れる機会が減り、知らず知らずのうちに視野を狭めてしまうのです。
もちろん、関心のある分野に没頭することは素晴らしいことです。しかし、ときには“未知”や“苦手”と感じるものに、あえて一定の期間身を置いてみることも、私たちの学びや成長においては欠かせない営みではないでしょうか。
惰性から解放されるということ
中高年になると、「これは苦手だから無理だ」「自分はこのやり方でやってきた」といった、思考の惰性からくる判断を下してしまいがちです。しかし、それは本当に正しい判断と言えるでしょうか。
かつて理解できなかったことも、今の自分なら違った視点で捉えられるかもしれません。なぜなら、私たちは当時とは異なる環境に身を置き、知識も理解力も経験も、すべてがアップデートされているからです。そう考えると、リスキリングの本質とは、単なるスキルの習得にとどまらず、「かつてはできなかったことに、いま改めて挑むこと」にこそあるのではないでしょうか。
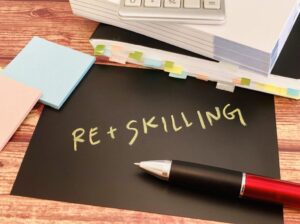
学びを再定義するということ
中高年が新たな学びに取り組むとき、それは知識を増やすこと以上に、過去の実体験と結びつくことで、学びそのものの“意味”が深まっていきます。
たとえば、学生時代に「テストのため」に勉強していた数学も、今の私たちにとっては、構造的な思考や論理的な整理、他者理解の手がかりへと“再解釈”できる対象になります。こうして、かつての「知る」は、「使う・伝える・受け止める」へと変容していくのです。
このような“再解釈・再構築・再定義”のプロセスは、自己理解の更新であり、これからの行動を変えていく土台ともなります。
“不得意”や“敬遠”に対する再挑戦は、新しい扉を開く起点になります。扉が開かれると、時間の使い方や出会う人が変わり、人生の風景そのものが少しずつ変化していきます。それは決して派手な変化ではありませんが、静かに、そして確実に、自分自身を変えていく力となるのです。
おわりに
「苦手だから」「今さら無理だから」と自分に貼ってきたラベルが、かつての限られた体験から生まれた、ただの思い込みだったとしたら、どうでしょうか。
ビジネスの現場においても、遠ざけてきた「苦手」の中に、これからの成長や貢献の鍵が隠れているとしたら?
このコラムが、あなた自身の思い込みをそっと手放すきっかけとなり、過去の学歴ではなく、“これからの学習歴”を更新する一歩に、そして新たな視点と価値を生み出していく始まりになれば、嬉しく思います。
参謀学Lab.研究員 青木 永一

